Dr.1512 健康第一(1月18日)
今さらながら、健康第一、健康の大事さを思っている。特に何かあったという訳ではないが、日々を元気に生きるためには、心身の健康があってこそ。もちろん、健康のために生きているのではないので、何をさておいても健康維持のためのトレーニングや食事療法とは思わないけど。
幸い、毎朝のランニング(世間的にはウォーキングのスピード)と勤務終了後の筋肉トレーニングは習慣となっているので、それほど無理をしなくても出来ている。食べ物に気を付けるのもそれなりに実行している。
後は睡眠時間の確保と精神的な安定だ。こちらの方は中々、いつも上々とはいかない。帰るのが遅くなったり、落ち込んだりする時がある。落ち込んでも事態が改善するわけではないので、気にし過ぎないように気を付けているが、油断するとつい弱気がやってくる。
特に、この頃中々調子よいなと油断した時に、ストレスが襲ってくる。日々機嫌よくの心の整え方、これが生きるテーマでもあるので、これからも実践しながらより良い考え方、身の処し方を見つけて行きたい。簡単には見つからないけど、それだからこそやりがいもあるし、少しでも改善すればそれは即自分自身の生き易さにもつながってくるので、やる甲斐もある。あれっ、少し前向きな考え方になってきましたね。この調子で今日も頑張ります。あっ間違えた、ボツボツ行きます。
☆友好都市交換マラソン激励会で、いつもの」「オー」。これ元気そうに見えますよね。ホントに元気かも。

Dr.1511 再会(1月17日)
今朝起きて、高校剣道部仲間のラインを覗いてみると、卒業してから会っていない部員仲間で現在はアメリカに住んでいる人からメッセージが届いていて驚いた。
他の仲間がいろいろと探してくれて実現したのだが、彼は早くから渡米して現地の人と結婚して、剣道インストラクターをしている息子さんと3人で暮らしているそうだ。
50年近く会っていない人に、ケータイを通じて会える。凄い時代になったものですね。生きてるといろいろ驚きの事態に巡り合えます。
ここはやはり何より元気で生きて、寿命が来るまで生きて、何が起こるか分かりませんが、その良い面を見て、淡々と生き抜くというのが良いようですね。機嫌よく生きる、それが幸せだと思っています。
☆送られてきたアメリカ住まい剣道部仲間の家族写真。幸せそうです。
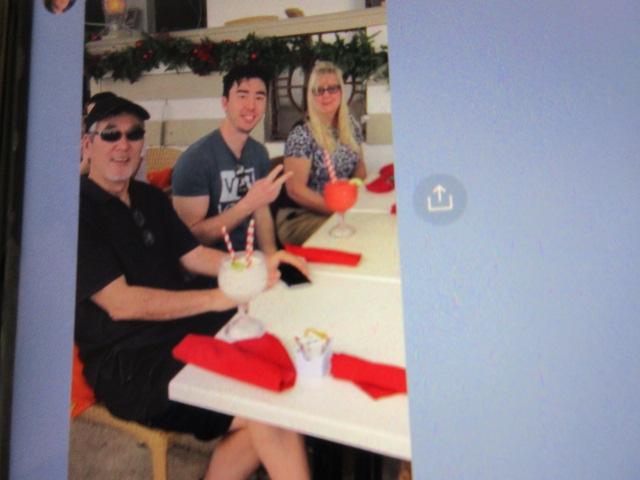
Dr.1510 目指すもの(1月16日)
第一の職業人生が終わった後、何を目指して生きるのか。生涯現役と言う人もいて、それはそれで素晴らしいとは思うが、医師とか学者とか作家とか特別な仕事の人には出来てもなかなか一般人には難しいかなと思う。
そんな時この頃考えるのが、身の丈に合った上機嫌な日々を生きるというものだ。主にはこの目標で生きるのだが、何%かは人の役に立つこともする。そのためには健康がやはり大事と言うことになると思う。
運動習慣については、幸い、そんな意識ではなかったが、若い時から毎日運動の習慣が出来ている。これはありがたいことで、これからも続けて行きたい。
後は心の平穏、嫌なことを忘れる、「まあいいか」精神で生きるということになるだろうか。このような、どう考えて、どう過ごせば、第2の人生が機嫌よく進むのかの研究、これをテーマに生きようかしらん。
これだと、生きるテーマもあるし、少しでもつかんだ成果(知見)は自分の生活にも活かせる。それを求めに応じて人にもシェアできれば、自分の有用感にもつながるし人の役にも立つ。この生き方いいではないですか。何でこんなことに今まで明確に気付かなかったのだろう。ボンヤリとは分かっていたので、研究を進めてきたような気もしてますけど。まあボチボチ行きますわ。この考え方もこれまでの探求の成果です。いうほどでもありませんけど。意外と真実は平凡なところにあるのかも。
☆選手としてはよう走りませんが、こんな新春駅伝の場にも参加できました。ありがたいことです。

Dr.1509 やっぱり趣味か(1月15日)
昨日の午前中は何も予定がなかった。雨で農作業も出来ず、本を読んだり、村の会計の仕事をしたりしたが、何か充実感がない。
午後からは八上城跡保存活用ワークショップに出かけた。中世山城の保存と活用に関する講義と参加者でのグループ意見交換だ。参加者の多くは歴史の愛好家で、自分でも歴史を研究したり現地に調査に行ったりしておられる。そしてお元気だ。
定年後の元気な生き方にはやっぱり趣味、しかも同好の士と集まる機会があるようなのが良いように思われる。昨日の皆さんは、自分の調査研究と研究会の参加などで顔見知りも多いようだ。
趣味がしかも人と関わる機会のある趣味が良いのは分かるが、さりとて自分が好まないものは趣味にはならない。これまでの経験からは、趣味に関わらずいろんな出会いから道が付いて行くことが分かっている。そんな出会いがやってくるのを待つか、自分で見つけに行くか。
待つか動くかも含めて、流れに任せよう。自分で動かず、まだ出会いの流れもない時は退屈が待っているが、それを味わうのも流れかもしれない。
☆史跡に関心のあるいろんな人が集まっていた。待つか動くか、それも流れに任せよう。心配もあるけど、まあ何とかなるでしょう。

Dr.1508 久しぶりの感覚(1月14日)
市内の高齢者大学で講話と言うほどのものでがないけどお話をさせてもらった。テーマは高齢期を生きるヒントみたいなもので、日頃から自分が関心を持って調べている分野だ。
人前であいさつや短い話しをするのはよくあるが、90分の持ち時間で、アクティビィティも入れながらやるのは久しぶりだ。今回の参加者の方は、もちろん高齢者だが、同じ地域にお住まいの方で、何度も講座を受けておられる方で、お互いにお知り合いで仲良しが多い。
そんなことで始まる前からいい雰囲気だったが、特にジャンケンや5チェンジ等のゲームが盛り上がり、逆に参加者の方に講師(ドクター)が、「皆さんが日頃大事にしてはることを教えてください」と聞いたのが良かったようだ。
こんなに盛り上がり、気持ちよく終われた講演会は久しぶりだ。これまででもベスト5に入る出来だったのではないか(よう覚えてませんけど)。こんなにうまく行くのなら、今後講師業で生きて行くのも悪くないなと思えるほどだった。
それでも、興奮が冷めると、いつもこんなにうまく行くわけがないし、そこそこ上手く行くのが続いても、それはそれで飽いてしまうのではないだろうかと、少し弱気も出て来た。こういう弱気を去って、楽しいコトプラスのことを数えて行こうというのが、講話の中心の一つだったはずなのに。
これもいつも言えることだが、自分が言ったり書いたりしていることは、先ず第一には自分に向かって言っている。今回も自分にとって気付きと学び元気をもらえた機会だった。こういうまとめ方は得意のお気楽な生き方なのだが。これが続かないのが課題です。
☆盛り上がった講演会。こんな講演会が出来るとは自分もまだ腕が鈍ってないなとすぐ調子に乗るお気楽な性格です。こちらを伸ばして行きたいです。


