Dr.484 声で分かる(10月22日)
先日某学校の外でそこの教頭先生と話をしていると、職員室から「聞き覚えのある声で『冒険』と聞こえたので(丹後さんだと思って)出てきました」と旧知の先生が顔を出してくれた。これ以外でも「声で分かりました」と言われることが時々ある。自分ではそれほど特徴のある声だとは思っていないが、多くの人からそう言われるからには特徴があるのだろう。自分のことは分かりにくいが、ドクターも声でその人が誰か分かる時がある。顔を見ればもちろんわかるが、声でも人を見分けられるのだ。もっと言えば、声だけでなく言い方や、発言の内容、考え方から服装や持ち物までその人らしさを構成している。今回の場合も、ドクターが当てられたのは、所かまわず大きな声でしゃべる遠慮のない性格と特徴のある声というのに加えて、『冒険』というキーワードがあった。この冒険という言葉は、顔や声の特徴や性格(お気楽)、態度・振る舞い方等と同じくドクターという人間を構成している大事な要素だということだ。せっかく長い間掛けて作ってきた、付き合いの長い自分と言う個性を大事にしながらも、流れで引き受ける新しい要素も加味してドクターらしい定年後の自分を作っていきたい。みなさんは、どんな声でどんな個性の自分を作って行きますか。
☆風呂好き(正確にはサウナ好き、もっと正確にはサウナでひと汗流した後のビール好き)もドクターの大事な構成要素の一つだ。

Dr.483 趣味を持つ(10月21日)
定年後生活充実のためには趣味を持つといいと言われる。特に将棋や囲碁はお勧めらしい。写真や絵画や歌などの趣味があると自分でも楽しめるし、同好の仲間との交流にもなる。趣味があると毎日が楽しくなるのは定年前でも後でも、若くても年寄ってても同じで、趣味を持つのは人生充実のためには良いことだということは分かる。そうだからとはいって、がんばって無理して興味もないのに趣味らしい活動をしても、それは趣味ではなく、苦行や仕事だろう。やっているうちに好きになることはあるだろうが、やはりとっかかりが敷居が高く、何かご縁がないと趣味活動に入りにくい。というわけでドクターは現在のところ趣味らしい趣味はないが、毎日身体を動かしたり、新聞や本を読んではブログネタを探したりしている。これも趣味と言えばいえるかもしれないし、ドクターの百姓も趣味の域を出ていない。百姓仕事はとてもプロとは言えないレベルだが、周りで垣間見るプロ百姓の仕事ぶりを見ていると(繁忙期には早朝から夜遅くまで作業をするなど)、とてもあのような打ち込み方はできないし、正直に言えばしたくない。自分のペースで田畑を耕し、ジムで汗を流すのと同じ感じで汗を流す。天の恵みがあった時には、農協に販売もするけどお知り合いの方にもおすそ分けする。そんな感じでやってるドクター百姓は趣味だろうか仕事だろうか、その境はあいまいだ。そういえば、ドクターの今やってる冒険指導や他の仕事も仕事と趣味の境はあいまいだ。こんな人には殊更趣味はいらないか。
☆趣味の山野草盆栽展。ここでも山野草の販売もあったりする。趣味と実益の境はもともと曖昧でいいのかもしれない。


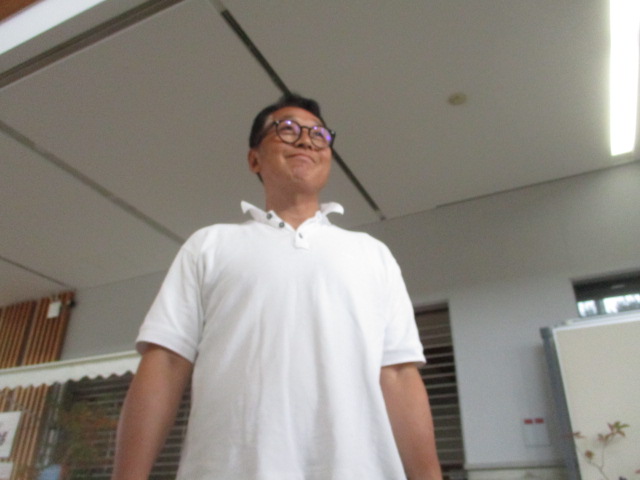
Dr.482 正解のない問い(10月20日)
今日の新聞に20代女性からの「これまでの小中高の学校生活では、テスト問題には必ず正解があり、学校生活や服装には校則があって正しい生活スタイルが明確だった。先生や親の言うことを聞いていれば間違い生き方が出来たのに、急に自分で考えなさいと言われて戸惑っている。誰かに人生の正解を教えてほしい」みたいな投書が載っていた。これまでずっと誰かの言われるとおりに、正解に向かって行動しいれば良かった生活に慣れた若者が、人生にも正解があってそれを示してほしいという気持ちは分からなくもない。しかし、こういう人にはきついかもしれないが、見方を変えればラッキーなことに人生に正解はない。いろんな答え(生き方・人生の目的等)があって、各自が自分で好きな答えを見つければいい。どっちの答えがより正しいかなんてないし、「答えを見つける旅を続けるのが人生」みたいな生き方があってもいい。投稿者の方は真面目な方で、ドクターと同じ匂いがするが、こんな方にこそドクターブログを見てほしい。ドクターもこの正解のない問いの自分なりの答えを見つける旅を続けている。見つかったと思ってもまた見失ったり、また見つけたりの繰り返しのような気がする。ただ、大切なことは答えが見つからなくても、決してやけを起こさず生き続けること。生きていれば見つかる事もあるし、見つからなくてもそれはそれで何とかなる。
☆小雨の中、人生をどう生きるのかと言う正解のない問いの答えを問い続けるドクター。視線の先には山頂がかすんだ人生と言う山が確かにそこにあった。


Dr.481 眠れない夜(10月19日)
昨夜と言うのか今朝というのか久しぶりに眠れない夜を過ごした。昨日は初めて講師登録させてもらっている団体から依頼された講演があったり、これまた初めて企業へ出向いて行っての指導があったり、その後地元まち協の会議や来年度の役員人事話し合いなど多彩な行事が重なった。依頼講演で行かせていただいた中学校の生徒たちは純朴でよく笑い声も出して活動に参加してくれ、特に食い入るようにドクターを見てくれていた女子生徒や最後の挨拶をした女子生徒、後ろの方で元気だった運動部系の女子生徒達、初めは「講演会は寝る」とつぶやいてたけど最後まで付き合ってくれた男子生徒などみんな可愛くてとても楽しくやることができた。その後の企業の指導も、皆さん勤務の合間を縫っての集まりであったにもかかわらず、よく付き合ってくださり満足だった。夜のまち協の話し合いは、来年度会長を受けなければならないかもしれない話も合って気は重いが、昼間の子ども達への講演で「人から頼まれたことは引き受けよ。自分の可能性を広げるから」と公言している手前、流れでやる羽目になったことはやらなければならない。やらないでも良い流れになることを祈るだけだ。それにしても、現役時代にはしばしば眠れない夜があったが、このところはとんとご無沙汰だったのにどうしたことだろうか。過去の記憶は美化されるというが、現役時代の楽しかったことばかりを思い出していたが、久しぶりに現役時代頻繁に眠れない夜があったことを思い出して、今の定年後お気楽人生の有難さを思った。それにしても昨日の多彩なイベントはすべて終わっているのに、なぜ今回眠れない夜がやってきたのだろう、その理由を考え出すとまた眠れなくなりそうだ。
☆久しぶりに眠れない夜を過ごしたドクターの乱れた寝室(こんなんだれもみたくないか)。眠れない理由ではないはずの楽しかった中学生や企業での指導の様子。



Dr.480 ゆる~い性格(10月18日)
いつも市民センターのトイレを掃除してくださる掃除のおばちゃまと何度もトイレで一緒になり(男子トイレ前の水道のところで、向こうは清掃作業、こちらはトイレ利用者として)、ドクターが「このごろ大も小も筋肉が緩んだのか、トイレへ行く回数が増えて困ってます」と言うと、おばちゃまが「ゆるいのは性格だけにしといてくださいよ」とおっしゃった。このおばちゃまはドクターと何度か話をしていて、ドクターがアバウトかつだいたいで生きるゆる~い性格であることをお見通しで、ゆる~い性格はいいが、身体が緩んでトイレが頻繁になったりするのは心配だということで、ドクターの健康を気遣って言ってくださったのだ。ドクターのお尻や膀胱の筋肉のゆるみは置いとくとして、ゆる~い性格を評価してもらったのが嬉しかった。長く生きていろんな経験を積んで来ると、人間そう理想・理屈通りには生きられないことが分かり、自分にも周りの人にもゆる~く接する方が生き易いことが分かってくるのだ。人それぞれなので、きつ~い人やかた~い人も必要だし、自分がその生き方で良ければ他人がとやかく言うことはないが、自分がきつくてもゆるくても良いように、他人のきつさ・緩さにも寛容であってほしい。特に自分がそうだから言うのだが、ゆる~い性格の人の存在を認めてほしい。よく人は自分と違う性格や
自分が嫌いなタイプの人を批判しがちだが、それでは世の中生きにくい。生き方の多様性を認めて、どんなタイプの人ともゆる~く付き合えるようになってほしいと、ゆる~い派を代表してお願いしたい。
☆ゆる~い性格代表でゆる~い着こなしのドクター。こういう人にはきつ~い奥様がついて丁度良い。


