Dr.2199 弱さを見せる強さ(2月13日)
女性活躍社会をめざす講演会を聞いた。アンコンシャスバイアス(無意識の偏見・思い込み)ということが言われ、女性だけでなく無意識のうちに「〇〇だからこれはできない。無理だ」などと思い込んで、その人の活躍の機会を奪っているのではないかということだった。
「女性だから重たいものは持てない」だとか、「若くて経験がないからこの仕事は任せられない」とか「時短勤務中の人だから、軽い仕事で」等と無意識に考えて(過剰な配慮で)、やりがいのある仕事から遠ざけているのではないかというのだ。
さらに、管理職のリーダーシップについても言及があり、今求められているのは、かつてのような何でもできる何でも知っている完璧なリーダーではなく、その人その人の持ち味を活かしたいろいろなリーダ像があって良く、中でも「自分の弱さも隠さず、自分もしんどい時があるので、あなたの気持ちはよく分かる」という、自分の弱さをさらけ出す強さを持ったリーダーも大事だということだった。
ドクターも常々、このブログをはじめ自分の弱さ、不完全さを表明しているので、「ヤッター 自分のやり方で良かったんだ」と意を強くした。時代がやっと自分のスタイルに追いついてきたのかという感じで、とても嬉しかった。
弱さを出すのを自慢するわけではないが、誰にでも弱点、しんどい時はあると思う。だからこそしんどい人の気持ちが分かるし、それにどう対処して行けばいいのかを共有できる。ドクター流で言えば、「無理し過ぎずボチボチ行こう」であったり、「自分の思いにこだわり過ぎず、流れとご縁に従ってやる流れになったことをたんたんとやっていく(できるだけ陽気に)」みたいなことだ。
これが強さと言われてもピンとこないが、自分が生きて行くために自分の心を安定させる考え方を探していくしかない。今回の講演会に限らず、いろんな人の意見も取り入れながら、今あることに感謝を忘れず、今日もボチボチ歩んで行きます。
☆生きていると(歩んでいると)こんな奇麗なシーンにも出くわします。皆様、今日もお元気で良い一日を。いろいろあると思いますが、いい面を見て行きましょう。

Dr.2198 柔らかく(2月12日)
時々、こうあらなければならないということに強くこだわる人がいて、対応に苦慮する。言われていることも分かるので、もう少し穏やかな提案なら受け入れやすいが、「絶対にこうしないといけない」と強く言われると弱ってしまう。
人には人の生き方、考え方があるので、そこにとやかく言うつもりはないが、問題はそういう柔らかさがない人とも付き合っていかなければならない、時に重なる時があるということだ。こちらが柔らかすぎるのが課題と言うこともあるのかもしれないが、ドクター的には柔らかく生きると言うことを大事にしている。
人には人の個性や生き方があるので、自分とは違っても「それもあり」と認めて行く。何事にもこだわらず、とらわれず、柔らかくいきたい。ひょっとしたら、「柔らかく生きる」ということに固くこだわっているのかもしれないが、そんなことはないはずなんですけど。
柔らかかろうが、固かろうが、こだわらず自然体で、流れとご縁に従って自分のやる流れになったことを出来る範囲で精一杯やって行く。いつも言ったり考えたりしていることだが、この柔らかい生き方考え方を自分は大事にしています。自分と違う考え方の人も受け入れる、懐の大きさも身に着けて行かなければということだろうと思うので、また自然体で修行して行きます。
☆先日の寒い日に見られた景色。自分の周りの良い景色、良い出会い今日も見つけていきましょう。


Dr.2197 意見を聞く(2月11日)
ウチの市長は「こんにちは市長室」や「お出かけ市長室」等で市民の意見を聞いておられる。昨日初めてその実態を見せてもらった。昨日の「こんにちは市長室」は16時から始まり、当日受付で先着順で話を聞かれる。一人(一組)15分が目安らしいが、30分くらいかかることも結構あるみたい。
私が同席させてもらったのは最初の方で、長年民生委員や民生補助委員をされてきたのだが、本年度で一区切りをつけられるにあたって、民生委員等と自治会のさらなる連携が必要と言うことを言っておきたいということで来られた。
地域の高齢者や援助を必要とされる方を把握し、災害などの緊急時に対応するために、民生委員と自治会(長)の連携が必要と言うことはよくわかる。市長は早速自治会を担当する部署の職員を呼び出して、必要な対応を指示されていた。すごい、素早い対応に感心した。
仕事はもちろん、日常の生活でも人の意見を聞くことは大事なことだ。ただ、厳しい意見も含めてどんな意見も聞くには、メンタル面での強さというのか、しっかりとした信念を持っていることが必要だ。ドクターの場合、まだまだ弱い所があるのでなかなか市長のようにはできないが、自分らしさを活かしながらやっていきたい。
☆カメラ設定を誤って、変な感じの写真になってしまいました。話し合いは明るい感じで進みましたので、写真のトーンとは関係ありませんのでご心配なく。
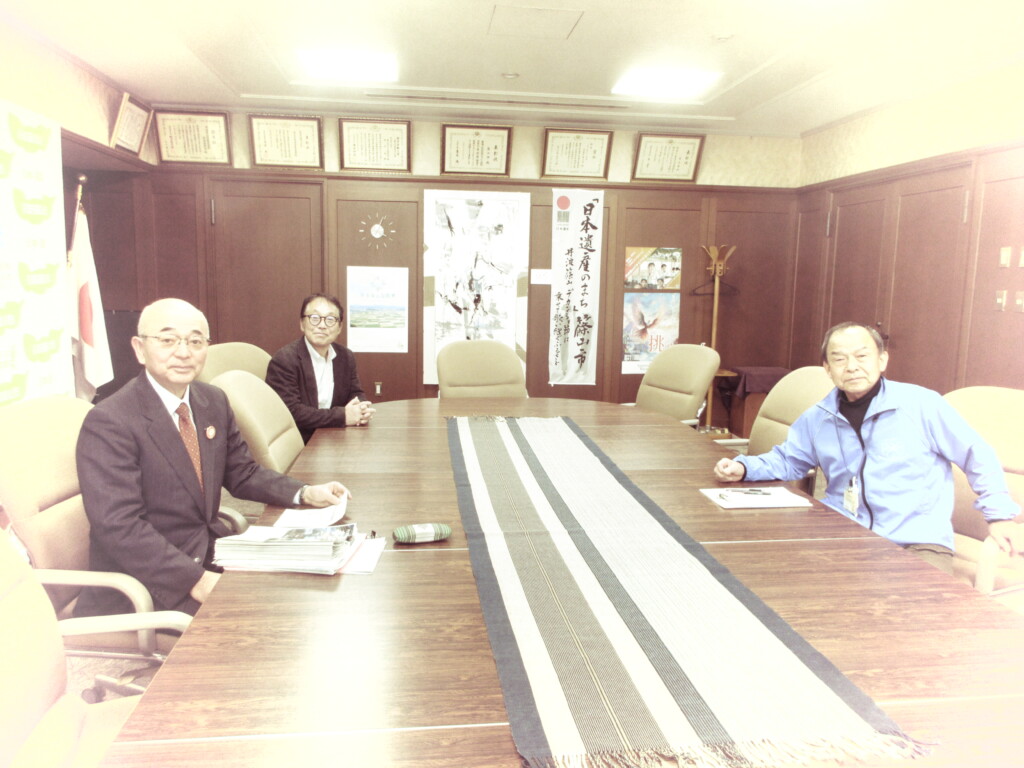
Dr.2196 日常の良さ(2月10日)
車の定期検査で神戸のお店へ行った。整備を担当してくれた、多分30代の若者が、自分も丹波篠山出身だと言うことで、いろいろ整備以外のことも話してくれた。その中で、高校の頃までは、丹波篠山は田舎で何にも無い所だと思っていたけど、離れてみるとその良さに気付いたというようなことを話してくれた。
その人は丹波篠山を離れて故郷の良さが分かったというのだが、同じようなことが他の日常でも言えるのではないだろうか。普段の生活、家族の存在など、いつもの日常を当たり前のこととして、そこは意識しないで、日々出て来ることを「ああだこうだ」と話題にしている。
日常の出来事も大事だが、その根底の日常の存在も、当たり前ではなく、いろんな幸運に支えられた有難いことだという意識を忘れないようにして、時々は思い出して感謝することから始めなければならない。
日常を当たり前、当然の存在として、その上に次は何、もっと何々がしたいと夢を膨らませていく。悪くないけど、その根底の有難さに気付かないと、無くしてから思い知ることになる。日常の大切さ、恵まれていることに感謝して、その上に自分に出来ることをやって行きたい。
整備の待ち時間にサービスで出されるコーヒーとスイーツをお代わりするという厚かましさはともかく、自分に出来る感謝と貢献忘れないようにして行きます。
☆ドクター部屋の窓から見えるいつもの景色。こんな当たり前も、いろんな幸運に恵まれ存在します。皆様、今日も一日感謝と自分に出来ることをやっていきましょう。

Dr.2195 平和の基本(2月9日)
平凡社を創設された下中弥三郎さんが呼びかてつくられた世界平和アピール7人委員会(かつては湯川秀樹・平塚らいてう氏らも参加)の講演会が丹波篠山市であった。下中さんが丹波篠山市今田町の出身ということで、近年では毎年丹波篠山市で講演会が行われている。
今回の講演会は、7人委員会の一人で作家の高村薫さんの講演と小沼通二さんらのパネルディスカッションがあった。
いろんなお話があったが、結局国際平和を実現するには人権尊重の精神が重要で、先ずは自分にできる周りの人のためにできる行動をするのが大事というようなことを学んだ。
考えて見ればその通りだが、ドクターが言う、生かされていることへの感謝と自分にできる貢献という考え方が、世界平和にも通じるということに改めて気付かされ意を強くした。大きなことでなくても、小さな声かけからでも、自分にできる自他への優しさ、暖かくする取り組みを進めて行くことが大事と言うことだ。
周りの人への優しさの中に、「自他」として、自分に対する優しさも入れているのはドクター流です。自分に優しく、自分を大事にすることから、人への愛情は広がって行くと思っています。皆さん、今日も自分に優しく、人にも優しくいきましょう。それがひいては国際平和にもつながるのですから。
☆昨日丹波篠山市民センターであった世界平和アピール七人委員会。閉会あいさつでの「世界平和への歩み、みんなで進めて行きましょう」「オー」には、いつもの丹波篠山市小学生野口君も参加してくれました。



