Dr.430 ちょっとした差(8月25日)
ぽっかり空いた予定なしの日、この過ごし方で定年後人生の過ごし方が決まると気合を入れていたが、最初楽しい予定があってそれが急になくなった日だっただけに、だらだら過ごすだけの嫌な予感一杯だった。それが結果的には息子と二人で今度のNHK大河ドラマの舞台になるであろう地元の高城山に登って、その後牛丼の昼飯を食べ、夕方関東へ帰る息子を見送って、夜は母と二人でいろいろ話しながらの夕食を食べるという結構充実した一日となった。これもその日の朝にSNSで見た冒険友人の「息子を山へ誘ったら乗ってきたので二人で山へ行く予定だ」という投稿がきっかけだった。その投稿に背中を押されて、NHK大河ドラマ推進委員長として前から気になっていた高城山の現状を見ておく登山に息子を誘ったら、さっと乗ってきて二人であたふたと準備して登った。登山自体は往復で2時間ほどのものだったが、環境が変われば会話も変わるという格言(丹吉師曰く)の通り、会話も弾んで良い夏の思い出になった。だらだらした嫌な感じの日になるか、ちょっと充実したすがすがしい日になるかの境目は、ちょとした切っ掛け(友人のSNS投稿を見た)と思いっきり(息子を登山に誘う)だった。それをするかどうかはちょっとした差だが結果として大きな差を生むことになった。そのちょっとした差を生むきっかけのSNS投稿をスマホで見たというのはたまたまだった。一日の流れの中でたまたまであった一コマが一日を決めたと言ってもいい。やっぱり流れとちょっとした思いっきりは大事だ。ちょっとした思いっきりをするかどうかも流れかもしれないし、その日偶然「息子を山へ誘う」投稿を見たのは天啓かもしれない。
☆息子と高城山へ登るという流れと天啓に従った行動で思わぬ好い日になった一日。山頂は森林組合による樹木伐採も進み眺望もよくなりつつあった。これも良い流れだ。関係者の皆様、天啓の方に感謝申し上げます。





Dr.429 ぽっかり空いた日(8月24日)
定年後の生活には何の予定もない空いた日を作らない方が良いと、これまで何やかやと予定を詰め込み馬車馬のように駆けてきたが、諸事情によりぽっかり空いた日ができた。そりゃあ世間は自分中心で回っている訳ではないので仕方のないことだが、最近では滅多になかったことだけにどう過ごしたら良いのか途方にくれている。当初は、本来ならやるはずだったことに思いを馳せてウジウジしていたが、時間と共にドクター哲学の「流れでやる羽目になったことを淡々とやって行く」が頑張り出し、空白でもやらなければならないこと(食べたり・寝たり・ブログを書いたり・・・)をぼつぼつやりだした。最初から休養のための空いた日ならそのように過ごせるが、本当は用事を入れたかったのに都合でできなくなって何も予定がないというのは結構厳しい。こんな日が続くと精神衛生上もよくない。定年後うつはこんな状態からなっていくのかとも思わされた。ここはこれからの生活が「うつ」か「お気楽か」の分かれ道と思って、空いた時間の過ごし方の研究と行きたい。ここでも身体を張った実験が続く。
☆急に何も予定が無くなった日、池の金魚を見つめながら「さてどうするか」と考えるドクター。今後の生活の試金石かもしれない。


Dr.428 ただ生きてるだけでも(8月23日)
旧知の知人に会おうと思い立ってその方の職場に立ち寄った。知人には会えたが、前日までは病気で休んでいたという。たまたま出勤してきた日にたまたま会いたくなった暇人ドクターがふらりと立ち寄り再会できたわけだ。たまたまの不思議さにも驚くが、聞けば以前にも生死にかかわる大病を経験されと言う。この頃ドクター周辺では、亡くなった方やうつ病で仕事を休んだり、家に閉じこもったりしている人、足の不調で歩けなくなったりしている人等何かのトラブル・不調・不幸に見舞われたニュースが多く入ってきている。中には人生を活き活き生きるために~にチャレンジしているというような景気の良い話も入ってくるが、釈迦がとっくに喝破された「人生は苦である」という厳しい真実を忘れてはならない。「人生は苦である」を前提にすれば、毎日が生きがいにあふれキラキラしていなくても、「ただ生きているだけ、特に大きな痛みや火急の困りごとがなく生かされている毎日」がどれだけありがたいことか。そうはいっても、生きている限り何も心配事がないという人はいないと思うが、心配事があっても何とか生きていることが出来ていれば、それだけでありがたいことだ。この感謝を忘れずに日々を生きる、まずそこを大事にしたいと再認識したお盆過ぎの蒸し暑い午後だった。
☆暇人ドクターが街をうろうろしていると、ライバルの丹波市で「2020年NHK大河ドラマ」に関するPRが華々しくされていた。丹波篠山市もがんばれと言う声もよく聞くが、こちらは出来る範囲で日々の感謝を忘れずボチボチやって行きたい。




Dr.427 葬儀をどうするか(8月22日)
ご近所のおばあさんが無くなり、村の人が集まり御葬儀の段取りを決めた。近頃はドクターの田舎でも家族葬も見られるようになったが、隣保のものが集まる村葬儀も多い。これを機会にうちの家でも自分たちの葬儀をどうするのかについて話が出た。妻は家族葬で良いと言い、ドクターは村葬でも家族葬でも流れで残った人のやりやすいようにやってもらったら良いと言ったが、妻は「あなたは派手好きだから大勢の人に集まってもらいたいんやろ。伴奏の曲には谷村新司の歌でもかけよか」と反論した。妻の答えにはまだドクターの理解が足りない。ドクターは現役時代何度かマスコミに登場したが、それは自分が目立ちたいからでも派手好きだからでもない、ひとえに自校の宣伝のためだ。かつて谷村新司のマネをし今もその名残のヘアーカットを続けているが、これも特別谷村さんが好きなわけでなく、当時の文化祭を盛り上げるためと惰性のせいだ。流れで葬儀の形を決めてほしいというのは、ドクターの生き方の総決算と言う意味も込めて本音だ。これまで流れで生きて来て、それで結構面白く生きさせてもらっている。できるならもう少しこういう生き方の良さを冒険指導や講演を通じて伝えて行って、最後は流れで死因も臨終の場所も決まればいい、特にこだわりはない。こだわらない生き方がドクター流生き方のこだわりだから。
☆この間の若者応援企画『夏映え』の記事が地方紙に載った。小さい記事をわざわざ取り上げるのはホントは妻の言うように目立ちたがりなのだろうか。
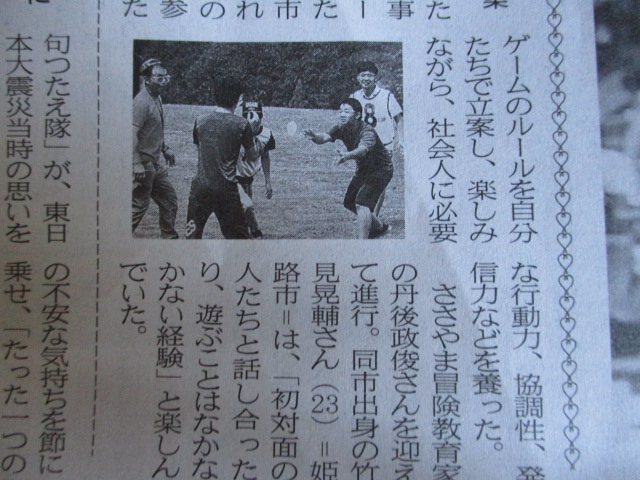
Dr.426 悪戦苦闘(8月21日)
SNSで入ってくる知り合いの情報には景気のいい話が多い。武者修行の指導でベトナムに言っているだの、自分を高めるために俗世間を離れて何日も座禅を組んだだの、朝活が充実しているだの、それら景気のいい話に比べるといつもの家で悪戦苦闘している自分が寂しくなる。野暮用で走り回った後、田んぼの草刈りを2時間して手足がつりそうになったり、夜間にハチの巣を襲撃してこちらも襲われたり、今朝など久しぶりに悪夢で目が覚めたり散々だ。幸いなのは記憶力の低下のお陰か悪夢の内容が思い出せないことぐらいだ。そして今日も何かと忙しいバタバタの一日で一日が終わるだろう。とここまでは自分の日常をマイナス面でとらえた書き方をしたが、自分にも恵まれたところは一杯ある(はずだ)。他人の調子のよい所と比べても仕方がないというのはこれまでの人生修行から得た教訓だ。人は人で大変なところも時期もある。日常はそう変化に富んでいないのが普通だ。ここは一つ日々の悪戦苦闘と格闘しながら時を紡いでいくしかない。また面白いこともやってくる時を信じて。
☆今朝はこんな感じで悪夢にうなされて目が覚めた(ような気がする)。今日も特に何ということがない皆さん、一緒にがんばっていきましょう。


