Dr.494 休み飽け(11月2日)
このタイトル「休み飽け」は「休み明け」の間違いではないかと思った人が多いのではないか。ドクターブログには間違いが多い(かつては親切な教頭先生が丁寧にチェックしてくださっていた)のでいつもの変換ミスだろうが、それにしてもタイトルからミスるとはドクター脳もいよいよ危ないのではないかと心配した人はさらにおおいだろう。ここで言おうとしているのは、久しぶりに自由な時間を神戸で過ごして楽しいことは楽しかったが、この休みも何度も経験すると飽きるだろうなという話である。贅沢な場所や贅沢な時間もたまにはいいが、毎回となると飽きてしまう(これを「休み飽け」と名付けたいのだ)。現実生活ではそんなことはあり得ないのでそんな心配をする必要はないのだが。ドクターの性格によるのかどうか、定年後生活には毎日用があって、しかもその用が毎日変わるのが良い。「貧乏暇なし」という言葉があるが、貧乏性・バタバタ酉年生まれ・実際には他人が思うほど収入がない自分には、この言葉がぴったりだ。暇なくバタバタ一日動いて、一杯飲んでバタンキューと眠る生活が最高だ。何も考えない、何もストレスがない、定年生活万歳、これを目指している。実際にはそうはいってもそれなりのストレスは生きてる限りやってくるが、その程度のストレスはあった方が良いとも聞く。ともかく目一杯フルタイム勤務しない身には土日も長い休みも必要ない。ということで今日もこれから出かけよう。用事があるのはありがたいことだ。
☆丹波篠山盆地名物霧の海の中に立つドクター。ゆったりした休みもたまにはいいが続くと飽きてしまう。「貧乏暇なし」が自分には合っている。


Dr.493 手帳が要るうちが華(11月1日)
来年の手帳を買いに町の文房具屋さんに行くと、80代と思しきご主人が「手帳が要るということは予定があるということで、予定があるということは何かの仕事や役に付いているということ。人から頼まれたり用があるということは、あんたがまだ人から必要とされている何かの役に立つ人間ということだから喜ばしいことだ。何の用もなく手帳が必要無くなったら寂しいもんだよ」みたいなことを語ってくださった。海馬が大分弱ってきているドクターにとって手帳はなくてはならないものだ。これがないと日々の生活が送れないと言ってもいい。特に冒険依頼などは手帳を見ないといつだったのか思い出せず、指導日をポカしてしまったら多大な迷惑をかける。温泉脱衣所の貴重品ロッカーには財布と共に手帳を入れるほどだ。このご主人に言われて、自分にも手帳が要らなくなる日が来ることに気付いた。確かに何の仕事もせず何の役にも付かなければ、手帳は必要ないか。その状態も寂しいが、何より飽き性のドクターには毎日同じような予定のない日々を送るのが耐えられないように思う。その点今年は12月までは手帳に空いた日がないぐらい予定(しょうもない予定も含めて)でびっしりだ。今予定があり、手帳が必要なことに感謝しながら、できるだけ長く手帳が要る日々を続けたい。
☆今年の手帳と来年の手帳を手に、文房具屋の親父さんが言われた「手帳が要るうちが華」と言う言葉に思いを馳せるドクター。

Dr.492 善意の連鎖(10月31日)
今朝ランニング(人はウォーキングと言う)をしていると、近所の人から農協の直売所で売れ残ったおもちを頂いた。この人は野菜や自宅工場で作ったおもちを毎朝直売所に出荷し、前の日に売れ残った分を回収してこられる。ドクターが走り歩きしていると、軽トラで後ろから近寄ってきて、「これあまりもんやけど」といいながら、おもちの10個入りパックを渡してくれたのだ。こんなことが時々ある。正直お餅大好き人間の息子が一人暮らしを始めてから、我が家ではそれほどお餅を食べる人間はいないので、頂いたお餅は近くに住む妹宅へおすそ分けすることになるのだが、この方の暖かい気持ちが嬉しい。たとえ売れ残ったものにしろ只で村のおっさんに分けてくれるというのは、そうできることではない。頂いたご好意・善意はしっかりとドクターの心に伝わり、今日一日がご機嫌でスタートできるとともに、自分にできる善意・人が喜ぶことは、できるだけしなければという気持ちになる。大したことはできないが、ドクターらしさを生かしたささやかな貢献をしよう、そしたらドクターの善意に触発されてまた善意の連鎖が起こるかもしれない。あまり連鎖を期待し過ぎるとわざとらしくなるので良くないが、それはともかく自分にできることを出来る範囲でやって行きたい。
☆頂いた善意のおもちと喜ぶドクター。善意と笑顔の連鎖が続きますように。大したことはようしませんけど、ぼちぼちやっていきますわ。


Dr.491 生きる理由(10月30日)
『生きる理由』『生きる目的』については様々に語られる。今回新たに「男はつらいよ」の寅さんが「生まれてきてよかったなって思うことがなんべんかあるじゃない。そのために人間生きてんじゃないのか」と語っているのを知った。これもいい言葉だ。普段はそんなにいいことにいっぱい出くわさないけど、1年に何回か「いいなあ」「良かったな」と思うことがある。後から思い出して何度も幸せな気分になれる。基本的には辛いことや苦しいことが多い人生だけど、時々幸せな時間・ことが訪れる。そんな時に生きてて良かったと思う。生きてないと出会えないのだから、普段は毎日良いことが起こるなどと期待しないで、たんたんと日々のしなければならないことをやっていく。するといつか分からないけど、たいていは突然に、思いがけないいいことが起こる。ドクターにも何度かそんな体験があるので、「生きてるといつかいいことがある」というのは間違いないが、ポイントはあんまり期待し過ぎないことだ。期待し過ぎるとなかなかやってこない現実に疲れてしまう。期待していない時にこそ、良いことや良い知らせがやってくるというのも体験から言える。さて今日も良いことが起こる期待は奥にしまって、たんたんと今日やるべきこと、やる羽目になったことに平常心で取り組んでいこう。
☆昨日知り合いの方から「悩んでいた時、ドクターが数年前に書いた文章で元気をもらいました」というようなメールを頂いた。こんなことがあるから生きているのかな。
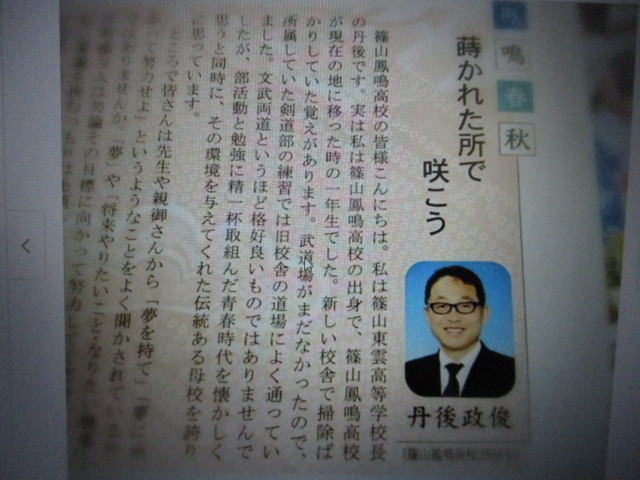
Dr.490 趣味を持てとは言うけれど(10月29日)
定年後は勿論、定年前でも人生の充実には趣味を持てと言われる。ドクターの周りでも歴史研究や茶道、ランニングにバイクに音楽演奏などそれぞれの趣味を楽しんでいる人は多い。趣味があると人生が楽しくなるのはよ~く分かるけど、問題はだからと言って趣味とは無理に持つものでもないだろうし、無理したとしても長続きはしない。趣味ってやっぱり、健康のためだからとか人生には必要だからとかいう理屈でやるものではなく、損得勘定を抜きにした好みの問題だろう。かくして、ドクターなどのように無趣味な人は「趣味を持て」「趣味があると楽しい」と声高に言われるほど肩身が狭くなるのを感じる。そこで今回は無趣味派を代表して「趣味がなくても元気に生きられる」ということを主張したい。もしかしたらドクターは、「ブログやSNSなどは威勢のいいことばかり書きすぎる」「無趣味で静かに生きてるけど、こんな失敗した、こんなことで悩んでますみたいな、マイナスなことも書け」「その方が人間らしいし、同じような逆境に生きる人には励みになる」みたいなことを主張するのが趣味かもしれないという懸念もあるが、趣味趣味と声高に言わなくても生きて行けるし、生きてると自然に見つかったり、自分で気が付かないうちにやってることが趣味だったりということもあるかもしれない。ドクターの場合も自分では趣味だとは思っていないが、冒険指導したり、毎日運動したり、ブログ書いたり、お菓子や菓子パン食べながらコーヒー飲むのも趣味と言えばいえるか。もっと言うと、寿命まで生きるのが趣味かもしれない。
☆昨日「八上城へいざ出陣」が新聞に載った。もしかしたらイベント参加好きも趣味かもしれない。趣味、趣味言わなくても好きなことをしてら結構人生面白い。それを趣味っていうんでしょうかね。無趣味派の弁護になったかな。



